こんにちは!ピアノ講師のみゆぽんです。
初めてピアノに触れる小さな生徒さんにとって、最初に使う教材はとても大切です。
でも、導入教材って意外とたくさんあって、

どれが使いやすいの?年齢によって合う教材は違うの?
と迷ってしまうことも。
この記事では、現役ピアノ講師の私が実際に使ってよかった導入教材を5つ厳選してご紹介します。
実際のレッスンでの使用感や、子どもたちの反応、指導者として感じたポイントも合わせて解説していきます。
レッスンでの使いやすさや、生徒の反応、指導者目線でのポイントもあわせて解説しています。
お子さんや生徒さんにぴったりの1冊を見つけるヒントになれば嬉しいです。
導入期の教材選びが大切な理由
「楽しい!」が最初にあると、ピアノが大好きになる
子どもにとって最初の音楽体験は、その後の音楽人生を大きく左右します。
ワクワクしながらレッスンを始められるよう、楽しくて達成感のある教材を選ぶことが大切です。
最初につまずくと「苦手意識」がついてしまう
難しすぎる教材や、退屈な内容だと、ピアノが「楽しくないもの」になってしまいます。
それが原因で辞めてしまう子も少なくありません。
導入期は、「できた!」の体験を積み重ねられるよう、無理のない進度・構成が必要です。
基礎力の差が、後々の成長スピードに直結する
読譜・リズム・指の使い方などの基礎をどれだけ丁寧に身につけたかで、次のステージの理解度が大きく変わります。
導入期に土台がしっかりしていれば、中級レベル以降の伸びが格段に良くなります。
保護者との信頼関係を築く最初のチャンス
導入期のレッスンがスムーズで成果が見えやすければ、保護者の信頼を得やすくなります。
「うちの子、ピアノ楽しそうに通ってます!」という声は、口コミや紹介にもつながります。
子どもの導入におすすめのピアノ教材
ピアノ ひけるよジュニア1(ドレミ楽譜出版社)
幼稚園や保育園で習う童謡や、家庭でもよく耳にする親しみやすい曲が多く収録されており、小さいお子さんが楽しく取り組みやすい構成です。
ジュニアシリーズは1~3巻で構成され、最初は片手から、両手奏や音域の拡大、リズムや記号の理解へと無理なく進めます。
おすすめポイント:
- 親しみやすいメロディーが多く、楽しく練習できる
- 先生や保護者と一緒に連弾できる伴奏譜が付いており、アンサンブルの楽しさを体験できる
- 各巻末に「しゅうりょうしょう(修了証)」が付いており、達成感を得られる仕掛けがある
メトードローズ上巻(音楽之友社)
フランス発祥のピアノ初心者向け教則本で、バイエルと並び長年愛用されてきたロングセラー教材です。
古典的なアプローチで、音楽の基礎を確実に身につけられるため、将来音楽の道に進みたい子には最適だと思います。
難易度はやや高めなので、年齢高めのお子さんや大人の初心者におすすめしたい教材です。
おすすめポイント:
- 最初から大譜表を学ぶため、読譜力や両手奏の基礎が早く身につく
- 合理的な進行と反復練習
- フランス民謡を中心に美しい曲が多数収録されており、テクニックのみならず表現力も磨かれる
バスティン ピアノパーティー(東音企画)
年齢の小さい子どもたちが音楽の基礎を楽しみながら学べるように工夫された教材シリーズです。
おすすめポイント:
- 右手と左手の確認、指番号、低い・高いの概念など、基礎的な内容からスタートし、自然に読譜や演奏の理解を深められる
- カラフルな絵本形式で、小さいお子さんも飽きずに使える
- 伴奏音源、併用曲集などの補助教材が充実している
まいぴあの ぷれ
ひらがなが読めない年齢の子どもでも取り組める教材。
4歳から使える「ぷれ」シリーズから始まり、段階的に「まいぴあの1」~「まいぴあの5」まで用意されています。
おすすめポイント:
- 絵本のようなオールカラーのイラストで視覚的に親しみやすいデザイン
- グーやパーで黒鍵をたたく「クラスター」から導入
- 無料ダウンロード可能な伴奏音源があり、リトミックとしても活用可能
ぴあのどりーむ幼児版
未就学児をターゲットに作られた導入教本で、段階的に音楽を学べる内容です。
難易度としては「ひけるよジュニア1」よりも進度が緩やかで、小さいお子さんには最適な教材です。
おすすめポイント:
- スモールステップで無理なく進められる
- 楽譜が大きい(1ページに4小節程度)ので小さいお子さんでも読みやすい
- 歌詞がついていて歌いながら楽しく学べる
導入教材を選ぶときのポイント3つ
年齢や理解度に合った内容になっているか?
子どもの発達段階に合わせた教材選びはとても大切です。
右と左の区別がつくかどうか、ひらがなが読めるかどうかなど、それぞれの「わかる」「できる」に寄り添った内容であるかを確認しましょう。
難しすぎても飽きてしまい、簡単すぎてもモチベーションが上がりません。
親のサポートが必要かどうか?
導入期の子どもたちは、レッスンだけでなく自宅練習でも「わからないこと」がたくさんあります。
特に幼児のうちは、保護者の関わりが欠かせないケースも。
教材によっては、親子で一緒に取り組むことを前提としているものもあるので、家庭のサポート体制も踏まえて選ぶと安心です。
先生が使いやすいかどうか?
教材がどれだけ優れていても、先生が指導しづらいと続けにくくなってしまいます。
進度の組み立てや補助教材との連携、ページ構成の見やすさなど、実際のレッスン現場で「使いやすいかどうか」も大事な判断基準です。
導入部分の説明が丁寧だったり、セミナーなどが頻繁に行われている教材は、日々の指導がスムーズになります。
ピアノ導入期は”楽しい”が一番
ピアノの導入期は、音楽の基礎を学ぶ大事な時期ですが、それと同時に「楽しい!」と感じてもらうことが重要です。
しっかりとした教材選びを通して、子どもたちに音楽の楽しさを伝えることができれば、ピアノのレッスンがますます好きになり、今後の成長にも繋がります。
この記事が導入教材を選ぶヒントになれば嬉しいです。
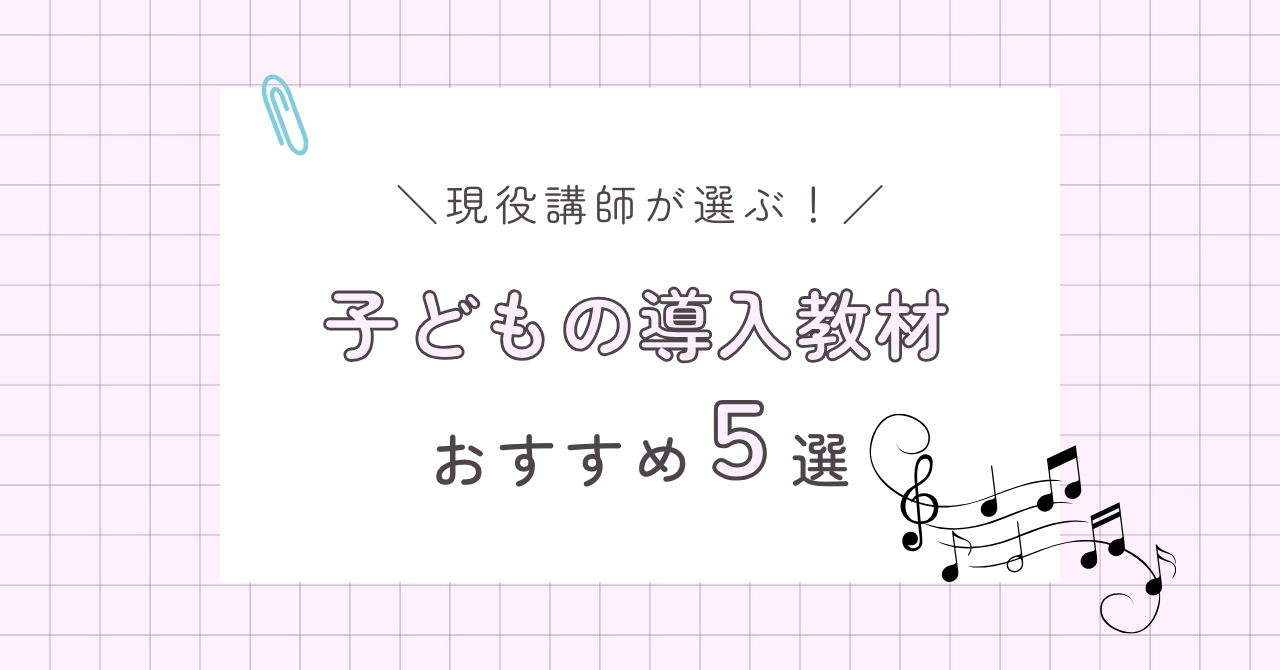
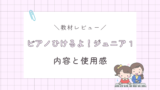
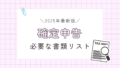
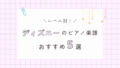
コメント